【管理職こそ副業しよう!】事業所得で加速させる知識と収入
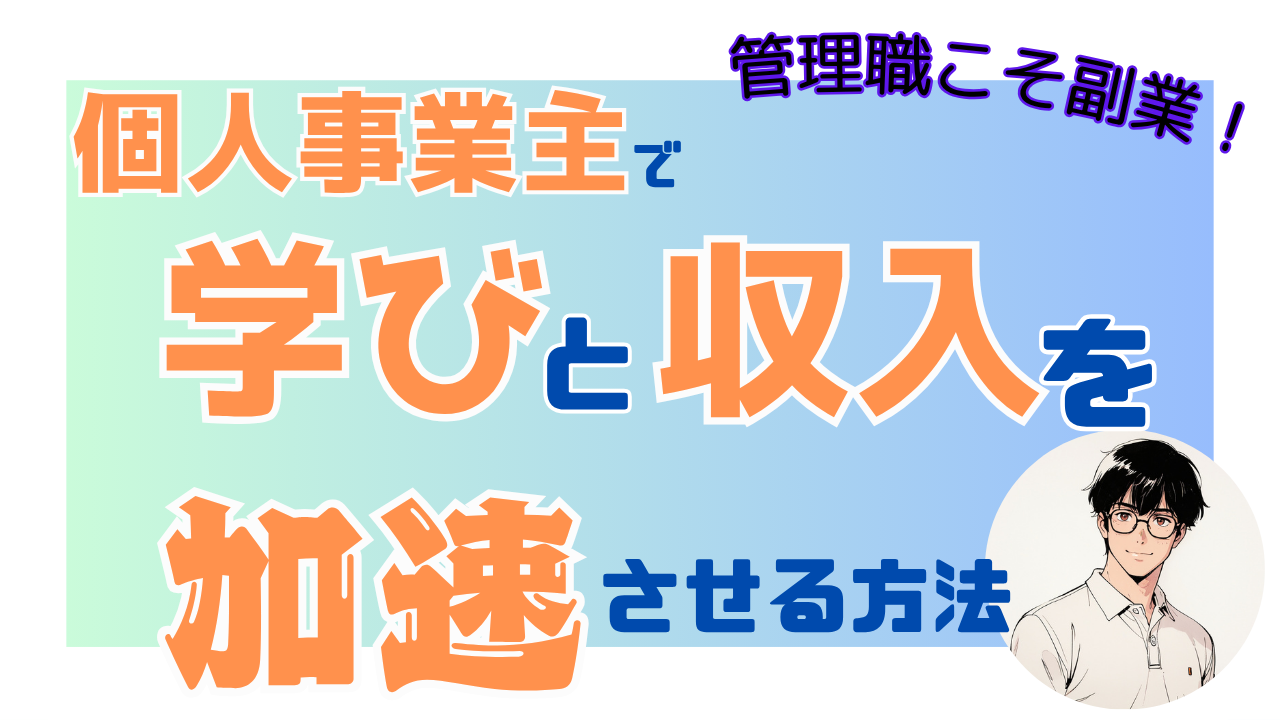
「管理職になってからも学び続けないといけない」
「でも、勉強するのもお金がかかる」
「それに、管理職になってから収入が伸びない」
このような思いのある方は、個人事業主として副業をしましょう。
個人事業主として事業所得を得ることで、確定申告をする必要があります。確定申告の際には、仕事の為の移動費や勉強費用を経費として計算して、課税所得をさげることができます。また、給料をもらっている先で社会保険に加入していれば、事業所得分には社会保険料はかかりません。
本業と関連性のある事業に取り組むことで、本業と副業でスキルと収入を上げていくことができます。
この記事では
- 給与所得×事業所得が収入アップに効果的な理由
- 勉強費用が経費になる個人事業主のポジション
- 誰でもできる個人事業主としての副業について解説します。

病院の理学療法士として、10年以上管理職をしながら、副業で月5万円程度の収入を得ていた経験をもとにして、事業所得の必要性と経費の考え方について解説します。
目次
給与所得×事業所得で資産増加が加速する理由3選!
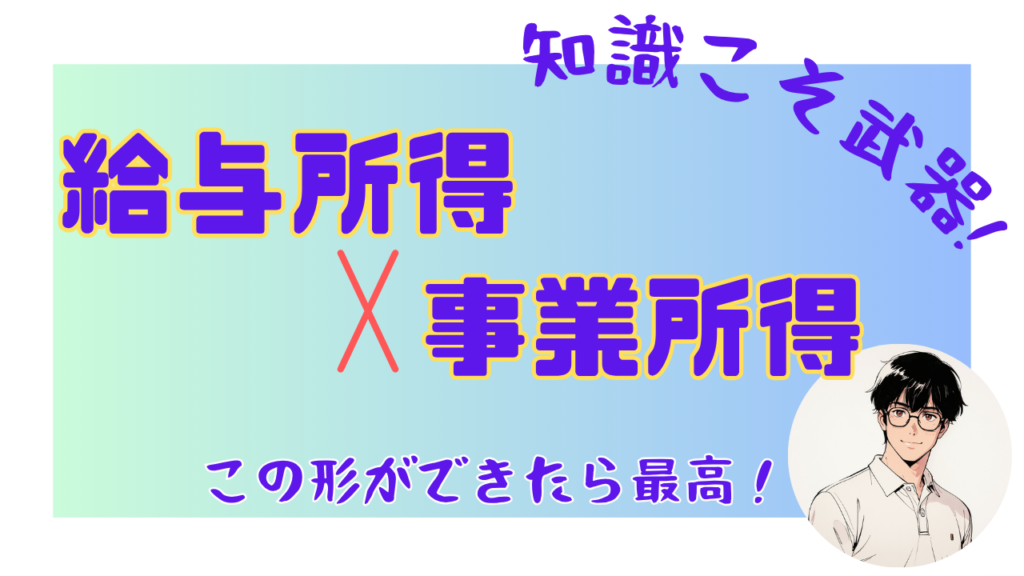
- 単純に収入が増加する
- 副業としての事業所得には、社会保険料がかからない
- 経費を計上することで節税になる
事業所得」という言葉を聞いたことがありますか?一言で言うと、自分でビジネスをして稼いだ「もうけ」のことです。この事業所得には所得税や住民税がかかります。では、社会保険料(健康保険や年金など)はどうなるのでしょうか?
本業で会社に勤めている方(給与所得者)の場合、社会保険料は主に本業の給料を基準に計算されています。そのため、個人事業主として副業で得た事業所得によって、本業の会社で天引きされる社会保険料が直接増えることは基本的にありません。
会社員の場合、社会保険料は下の公式で計算します。
毎月の保険料 = 標準報酬月額 × 各保険料率
つまり、会社員としての給料が高くなればなるほど、保険料も高くなると言う仕組みです。
かんたんな一例ですが、年収400万円の方が、給料所得として100万円昇給した場合と、事業所得として100万円増加した場合とで、社会保険料はどのように変動するでしょうか?
| シナリオA(給与+100万円) | シナリオB(事業+100万円) | |
| 年収の内訳 | 給与 500万円 | 給与 400万円 + 事業所得 100万円 |
| 年間の社会保険料(本人負担額) | 約76.6万円 | 約61.7万円 |
| ベースからの増加額 | 約14.9万円 増加 | 0円(変わらない) |
アルバイトという働き方は給与所得になるので、社会保険料が増加してしまいます。そのため副業を考えたとき、収入面で見て事業所得を得たほうが有利になります。
経費の考え方で賢く節税しよう
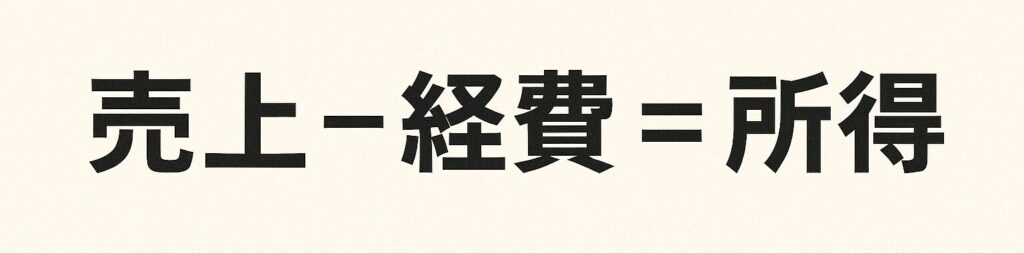
副業で事業所得を得ることがお勧めする理由の1つに経費を使えることが挙げられます。お金を稼ぐために必要な費用を経費として売り上げから引いたら事業所得ですになります。会社に雇用されているサラリーマンにはない考え方ですよね?
例えば
- 八百屋さんなら…
- 野菜を農家から買うためのお金(仕入れ代)、お店の家賃や電気代、野菜を入れるレジ袋代
- 漫画家さんなら…
- ペンやマンガ原稿用紙、インク代、仕事場の家賃、手伝ってくれるアシスタントさんへのお給料
- リラクゼーションセラピストなら…
- 調整のためのスマホ代、店舗の移動のための移動費
これらの必要経費を売上から引くことで本当に儲けた金額を計算します。
副業の節税は「経費」の理解から!生活費の一部を経費にする考え方
副業を始めたら、なぜ「経費」の理解が重要なのでしょうか?それは、これまで「ただの生活費」だと思っていた支出の一部を事業の「経費」として計上し、納める税金を抑えられる可能性があるからです。
例えば、以下のような支出が経費として認められます。
- 家賃や通信費: 自宅で作業する場合、家賃やインターネット代の一部を「家事按分」して経費にできます。
- 交通費: 打ち合わせなどで使った電車代や、車で移動した際のガソリン代なども対象です。
- 勉強代: 「この本の内容が、〇〇の案件に直接役立った」というように、事業との明確な関連性を説明できる書籍代や研修費は経費になります。

【最も重要な注意点】 もちろん、何でも経費にできるわけではありません。大原則は「その支出が、事業の売上を上げるために直接必要であったか?」です。プライベートな買い物や、事業と無関係な自己啓発のための勉強代は経費として認められないため、注意しましょう。
経費を正しく計上することは、節税への第一歩です。日頃から領収書を保管し、何に使ったかメモする習慣をつけましょう。
【どんな副業をすればいいの?悩むあなたにオススメの副業!】
副業を選ぶ上での基本的な考え方は、以下の3つです。
- 個人事業主として、事業所得が得られるか
- 本業との相乗効果が期待できるか
- 心から「好き」「興味がある」と感じられるか
これらは重要ですが、それでも「何から始めよう…」と悩む方には、まずリラクゼーション・セラピストという選択肢を提案します。
私自身も取り組んだ経験がありますが、この仕事には以下のような魅力があります。
- 低コストで開始可能: 大きな初期投資は不要です。
- 充実した研修制度: 未経験からでもプロの技術を学べます。
- 働き方の自由度が高い: 「週一回・1時間から」といった柔軟な働き方が可能です。
特に、全国600店舗以上を持つ「りらくる」のような企業では、そのシステムを活かしたユニークな働き方もできます。 例えば、県外の勉強会に参加する際、滞在中に現地の店舗で働くことで、滞在先から店舗までの交通費など、事業活動に直接かかった費用は経費として計上しやすくなります。

身体に関わる勉強をする理学療法士の場合は研修内容がリラクゼーションに活用できる内容のものも多いため、研修費自体も経費にできる場合も多いでしょう。
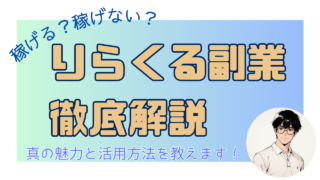
【それ以外の副業には何がある?】
副業は、大きく「インターネットを活用するもの」と「そうでないもの」に分けられます。
- インターネット系: YouTube、Webライター、ブログ運営など、PC一つで始められるものが多いです。
- リアル系: 自身のスキルを活かして直接サービスを提供するものや、企業から「業務委託」として仕事を請け負う形があります。
「インディード」や「クラウドワークス」といったサイトで、どんな「業務委託」の仕事があるか探してみるのも良いでしょう。
私が実践してきたオススメ副業をこちらの記事でまとめています。副業選択に悩む方の参考になります。
【良いことばかりじゃない!副業のデメリット】
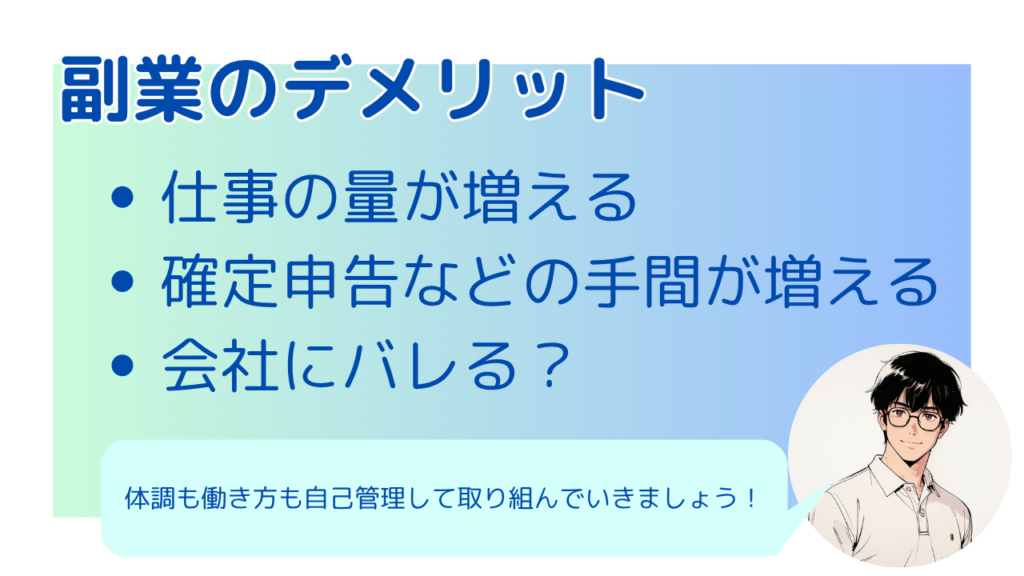
もちろん、副業には大変な面もあります。
- 単純に労働時間が増え、疲労が溜まる
- 確定申告など、自分でやるべき事務作業が増える
また、「副業バレ」をデメリットと感じる方もいるでしょう。 公務員は法律で副業が原則禁止されていますが、民間企業では副業を認める会社が増加しており、国も副業を推進しています。 まずはご自身の会社の就業規則を確認し、定められた手順に沿って申請することで、仮に知られても問題ない状況を築くことが可能です。
規則を正しく理解し、適切に行動することで、自分にとって有利なポジションを築いていきましょう。
まとめ:管理職こそ副業しよう
会社員が給与に加えて「事業所得」を得る副業を始めると、以下の3つの理由から資産形成を大きく加速させることができます。
- 単純な収入の増加: 本業の給与に、副業の収入が純粋に上乗せされます。
- 社会保険料の負担が増えない: 会社で天引きされる社会保険料は、あくまで本業の給与を基準に計算されます。そのため、副業で事業所得をいくら稼いでも、この社会保険料は**原則として増えません。アルバイト(給与所得)で同額を稼ぐ場合に比べて、手元に残りやすいという大きなメリットがあります。
- 「経費」の活用で節税できる: これまで「生活費」だった支出の一部を、事業に必要な「経費」として計上できます。自宅の家賃や通信費の一部(家事按分)、事業で使う交通費や書籍代などを売上から差し引くことで、課税対象となる所得を抑え、結果的に所得税や住民税の節税に繋がります。
副業を選ぶ際は、このようなメリットを最大限に活かせる「個人事業主」として始められる仕事**がおすすめです。例えば「リラクゼーション・セラピスト」のように、低コストで始められ、本業の知識も活かせる仕事は、最初の一歩として非常に有効です。
もちろん、確定申告の手間や労働時間が増えるといったデメリットもありますが、会社の規則を確認し、経費の知識を正しく身につけることで、賢く収入を増やしていきましょう。




